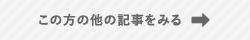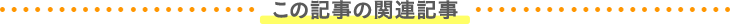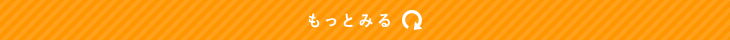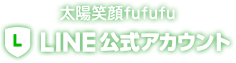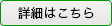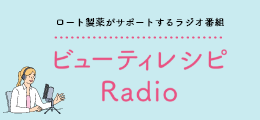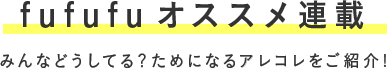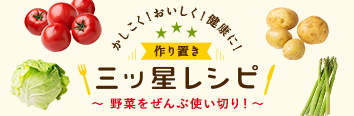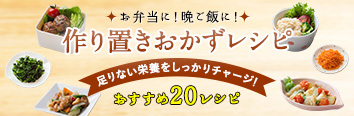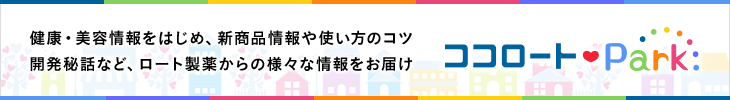本当のおいしさに出合える!鈍った味覚をリセットする方法。
栄養不足でも味覚が鈍感に!
摂り続けることで、その味覚に鈍感になる。特に、脂肪味はほかに比べると、やみつきのような状態になりやすいのだそうです。ただ、鈍感になってしまったとしても、脂肪味のセンサーは、リセットすることができるそうです。
「やはり、摂り過ぎないことです。脂質の摂取目標は1日60gが目安。1食20gを目標にするととり組みやすいと思います」
下にある表は、よく食卓に上る料理の脂質量。とんかつは、なんとそれだけで1日分の上限に近くなります。
定番の料理に含まれる脂質量
(一人前の脂質量)
- ご飯(180g)…0.5g
- 味噌汁(豆腐とわかめ)…2.2g
- バタートースト(5枚切り食パン)…7.1g
- 目玉焼き…17.6g
- ゆで玉子…10.4g
- コーンスープ…3.9g
- とんかつ…53.9g
- から揚げ(6個)…27.2g
- 鮭の塩焼き…8.9g
- 鯖の塩焼き…15.3g
- ぶりの照り焼き…16.1g
- まぐろの刺身・赤身4切れ…1.8g
- まぐろの刺身・トロ4切れ…6g
- 鶏の照り焼き(皮あり)…30.4g
- 鶏の照り焼き(皮なし)…12g
- 野菜炒め…4g
- 肉じゃが…17.6g
- ポテトサラダ…22.6g
- ハンバーグ…18.3g
- カレーライス…23.1g
- 親子丼…13.6g
- 海鮮丼…8.9g
- 餃子…17.6g
- 酢豚…8.3g
- 紅白なます…0.4g
- 大根とかいわれのポン酢サラダ…0.2g
- ご飯と味噌汁に鮭の塩焼き、紅白なますで、脂質は12g
- ご飯にハンバーグ、大根とかいわれのポン酢サラダで、脂質は19g
- ご飯と味噌汁に鶏の照り焼き(皮なし)、千切りキャベツ(+ノンオイルドレッシング)で14.9g 皮つきの場合は半分にすれば、18.1gに
「脂肪味の感度を上げる工夫(下にある表を参照)も、参考にしてください。この方法でできるだけ脂質を減らす食生活を、まずは10日間続けましょう。早ければ3日くらいで、脂肪味に対する感覚が変わったと実感できるようになります」
脂質を摂り過ぎないようにするあまり、欠食してしまうのはよくありません。感度を上げる効果が得られないことがあるそうです。
「脂質を摂り過ぎることだけでなく、控え過ぎることでも感度が鈍る可能性が指摘されています。以前行った調査で、脂質を抑える食生活を10日間続けた人の中で、数名が改善しなかったということがありました。さまざまな理由が考えられますが、そのひとつに欠食が挙げられます。メカニズムは明らかになっていませんが、飢餓状態になると、どんなものからでも栄養を摂ろうとするために、味覚の感度を下げるのかもしれません。これは脂肪味に限らず、基本五味も同じことが言えます」
朝食を抜いたり、夕食を控え過ぎたりせず、栄養不足にならないようにしましょう。
脂肪味の感度を上げる工夫。
- 揚げもの(菓子類を含む)を控え、調理法を焼く・蒸すにする
- 脂肪の多い肉を控え、赤身肉、鶏むね肉、魚を選ぶようにする。まぐろのトロは脂肪が多いので要注意
- 麺類はとんこつラーメンを控え、うどんや蕎麦、あっさりしたラーメンを選ぶ
- お菓子は洋菓子より、和菓子を選ぶ
- サラダにはマヨネーズではなく、ノンオイルドレッシングを使う
- 牛乳などの乳製品は、低脂肪のものを選ぶ
- カレーライスや中華料理を控える
- 串焼きは、鶏皮、豚バラ、ホルモン以外を選ぶ
- コンビニやスーパーの弁当や惣菜は、栄養成分表示を確認する
お口のケア、よく噛む。それも、味覚の維持に。
「オーラルケアも大切です。舌に汚れがあると味覚センサーである味蕾の働きが悪くなります。舌クリーナーを使って、舌苔をとり除きましょう。ただ、舌のこすり過ぎもよくありませんから、1日1度で。舌クリーナーを10回動かす程度でいいかと思います」
さらに、唾液の分泌を促すために、食事をよく噛むことを心がけましょう。
「唾液は、食べものの味のもとになる物質を味蕾に届ける役割があります。ですから唾液の分泌が悪くなると味を感じにくくなります。これも脂肪味に限らず、どの味覚もそうです。唾液にはほかに、噛み砕いた食べものをまとめ、嚥下をしやすくする働きもありますから、おいしく食べるために欠かせないものです。よく噛むことに加えて、うま味を感じることも唾液分泌を促します。だしをはじめ、うま味のある食品が役立ちます(下にある表を参照)」
筆者も早速実践しようと決意しました。食事をおいしく食べられるのは、幸せのひとつ。そしてそれは、健康にもつながっていきます。おいしいものを楽しめる未来のために、味覚センサーを大切にしていきましょう。
うま味物質を含む食品。
定番の料理に含まれる脂質量
昆布、チーズ、白菜、トマト、アスパラガス、ブロッコリー、玉ねぎ、醤油、味噌など
イノシン酸
鶏肉、牛肉、かつお、かつお節、豚肉など
グアニル酸
干し椎茸、えのき、海苔、ドライトマトなど